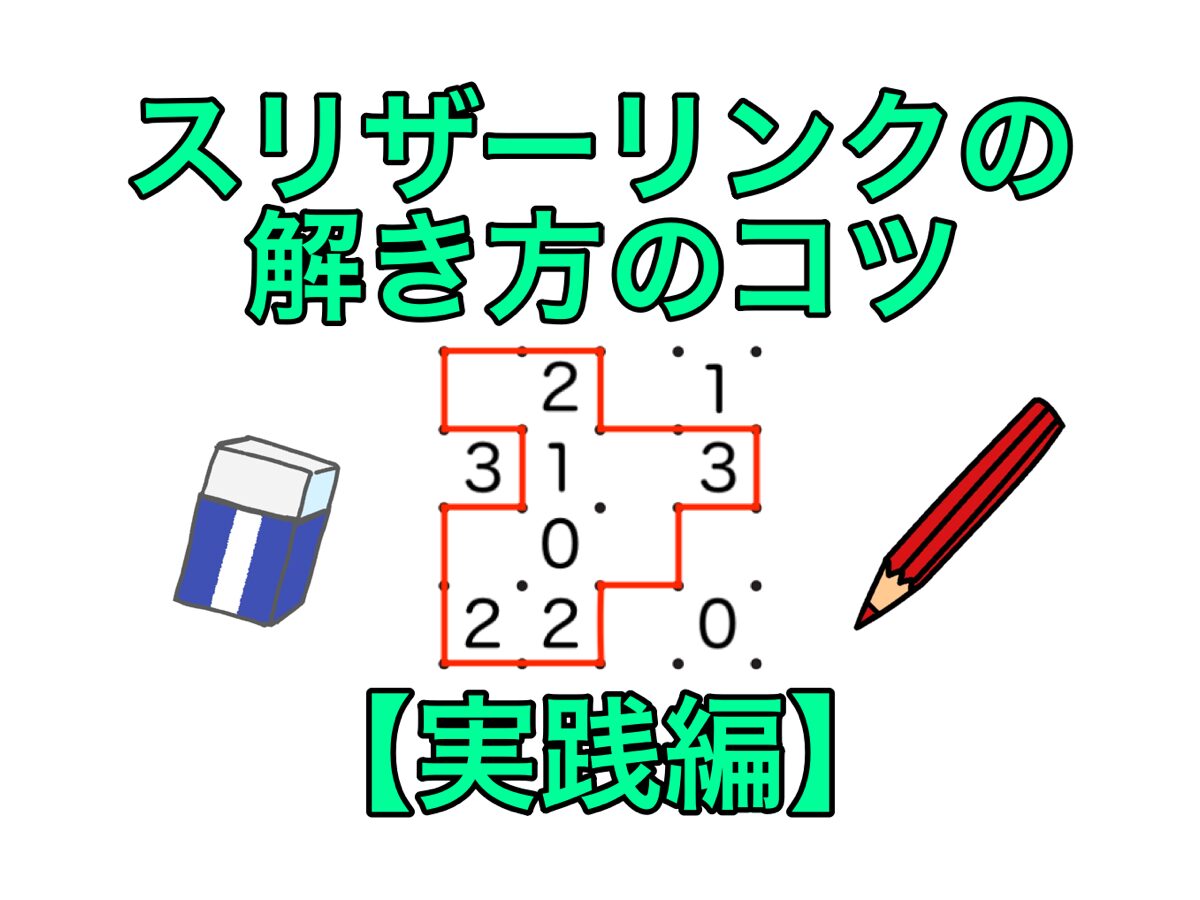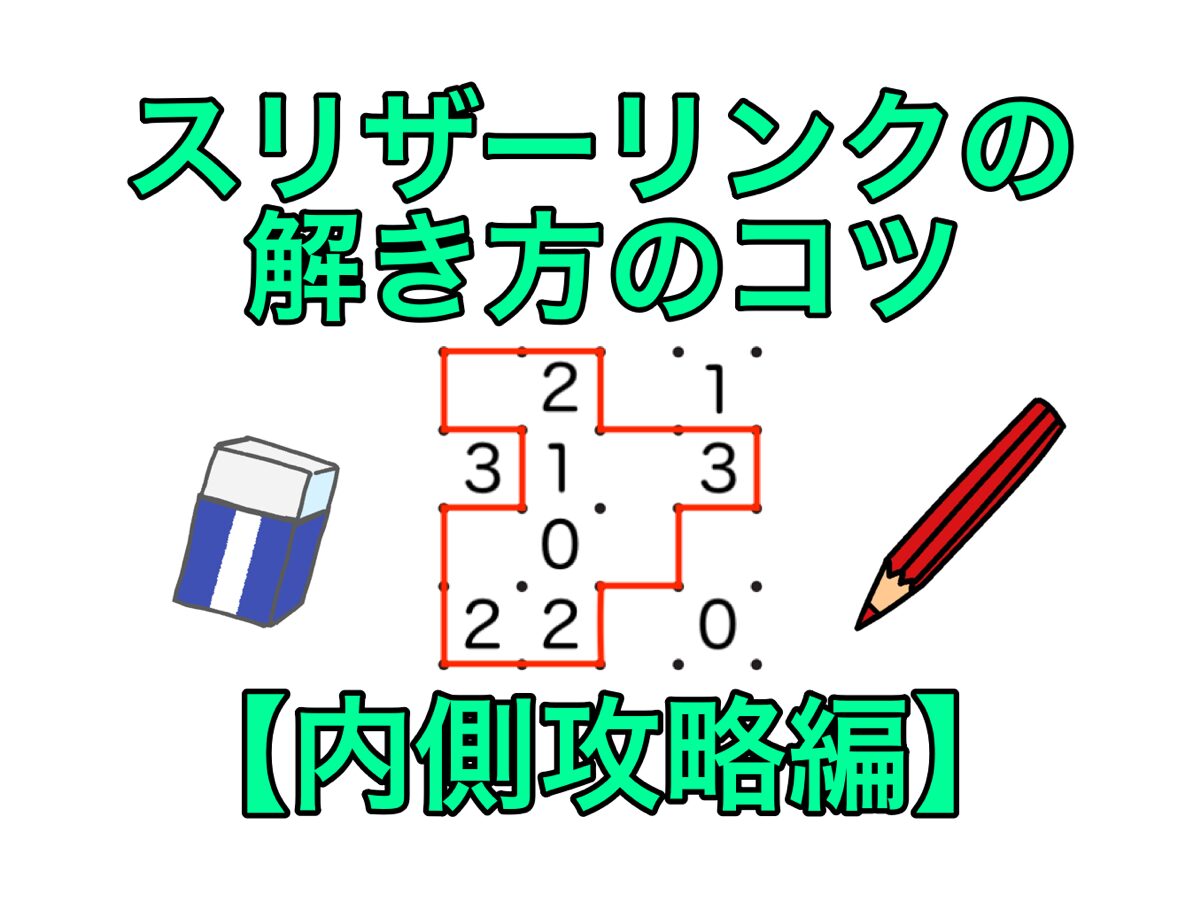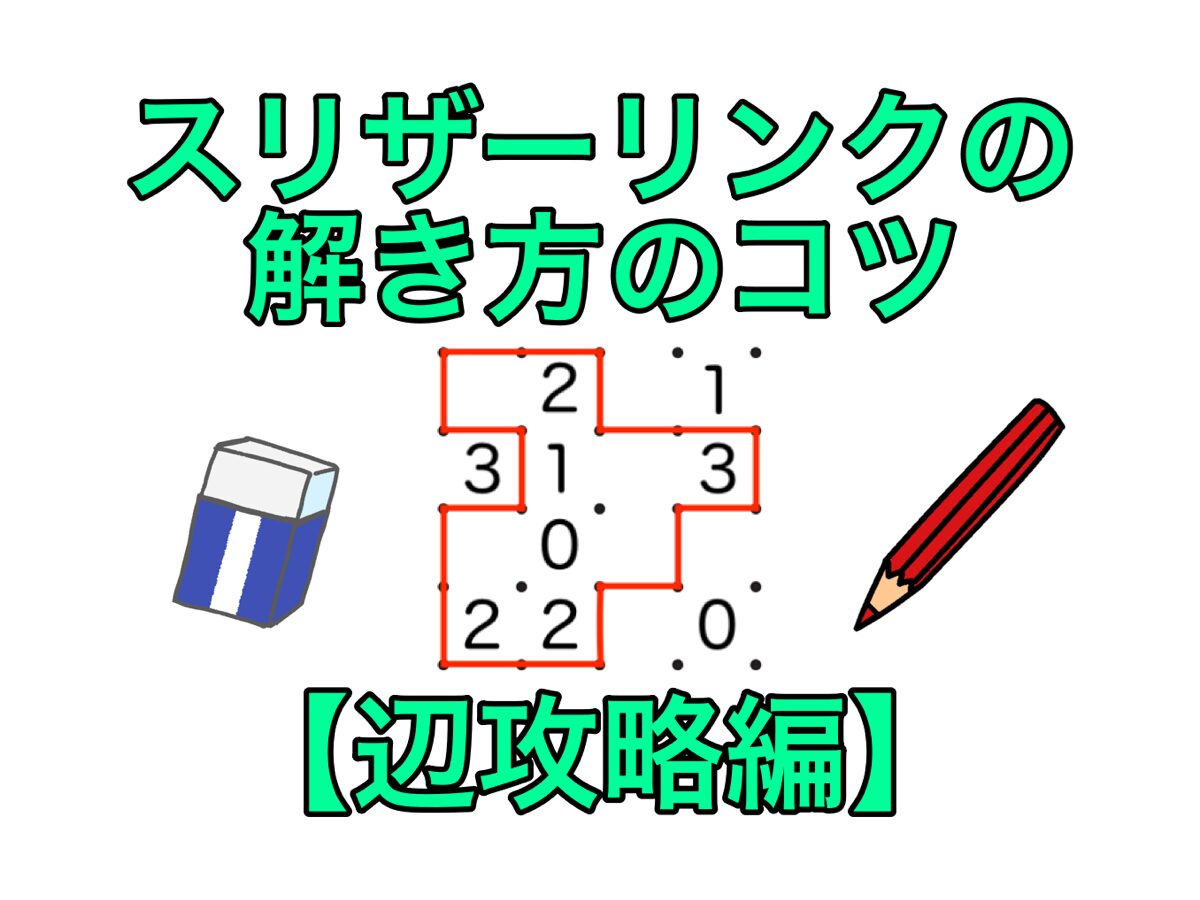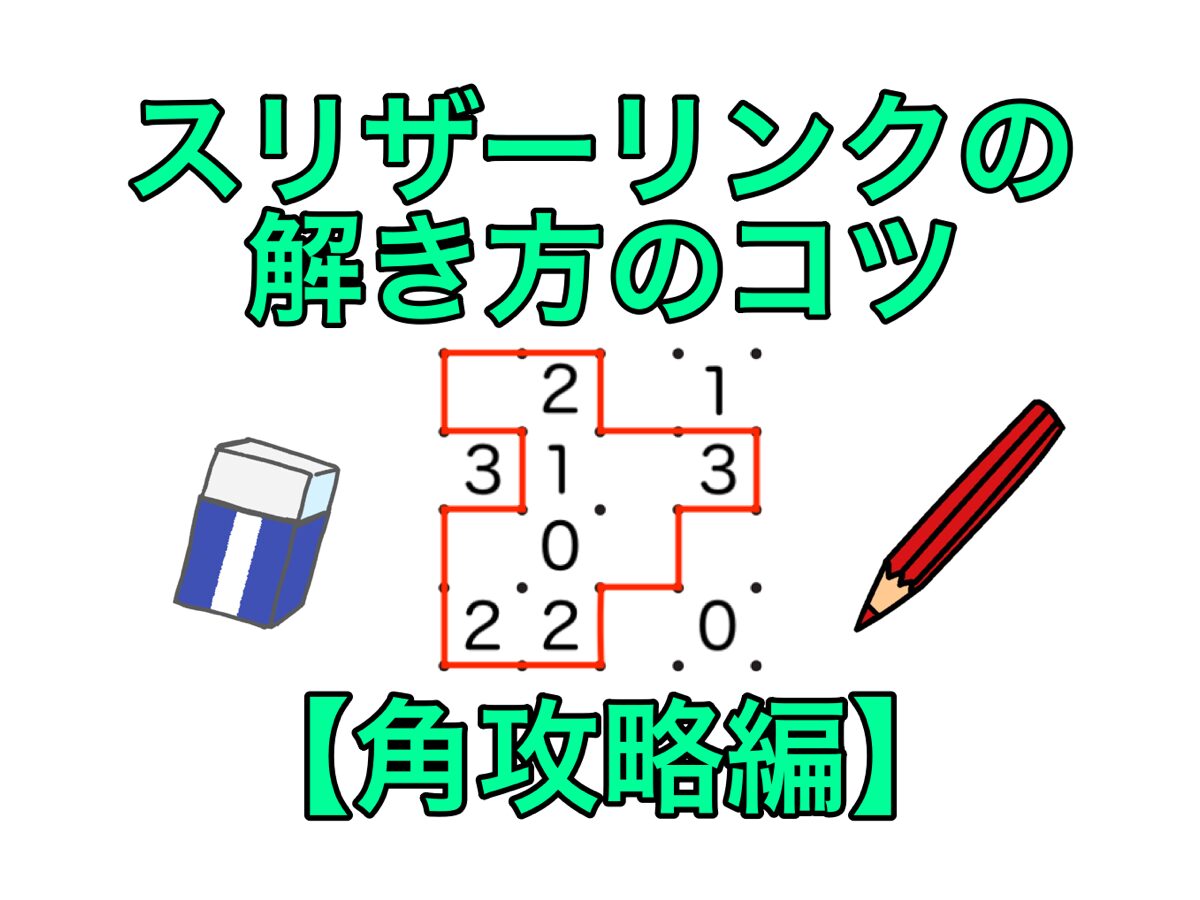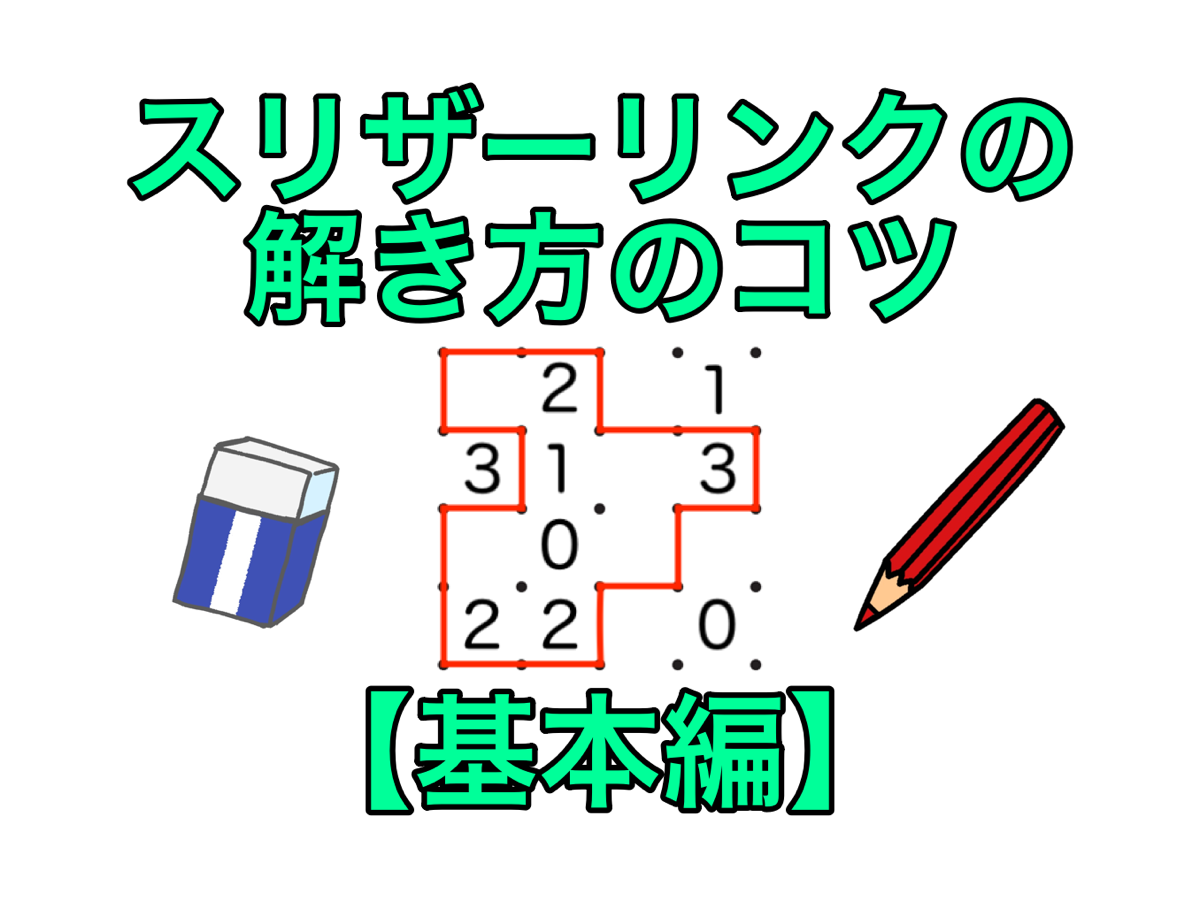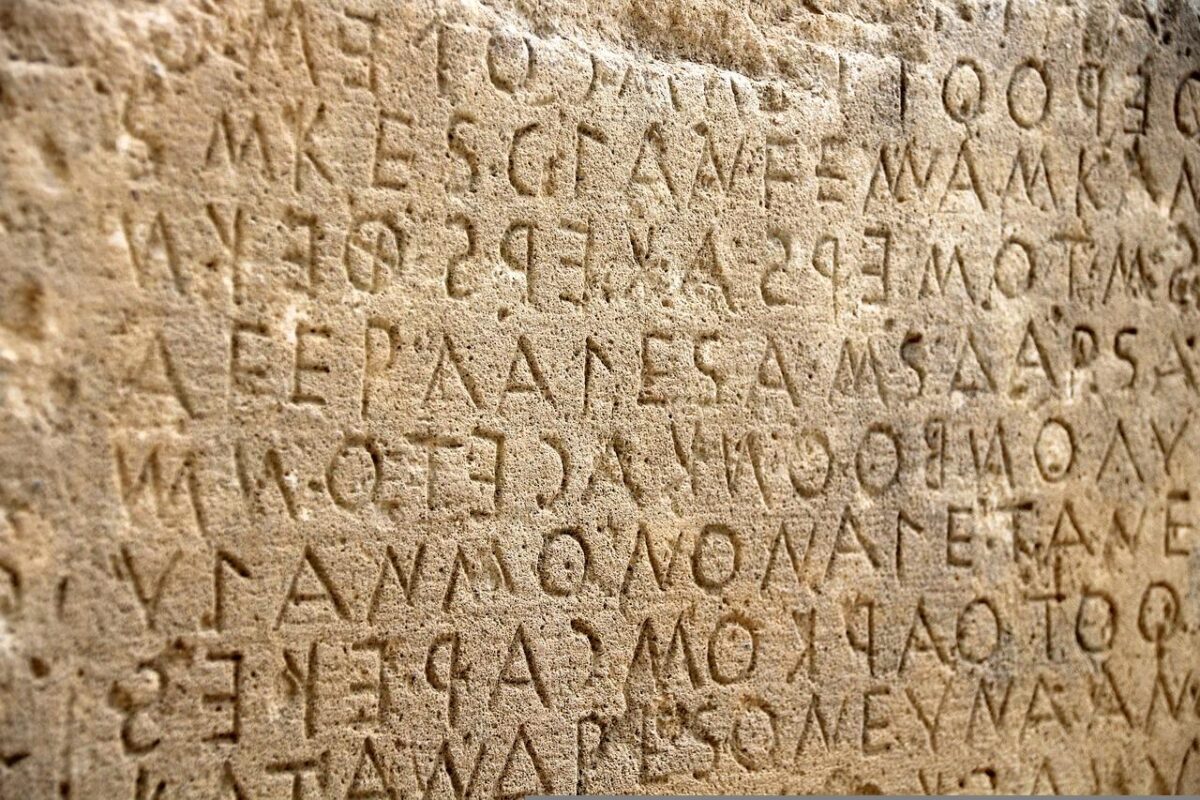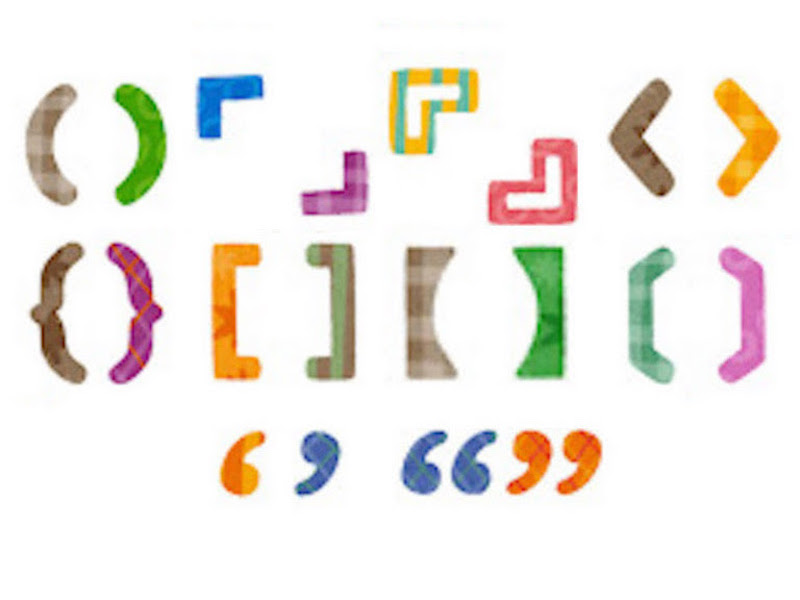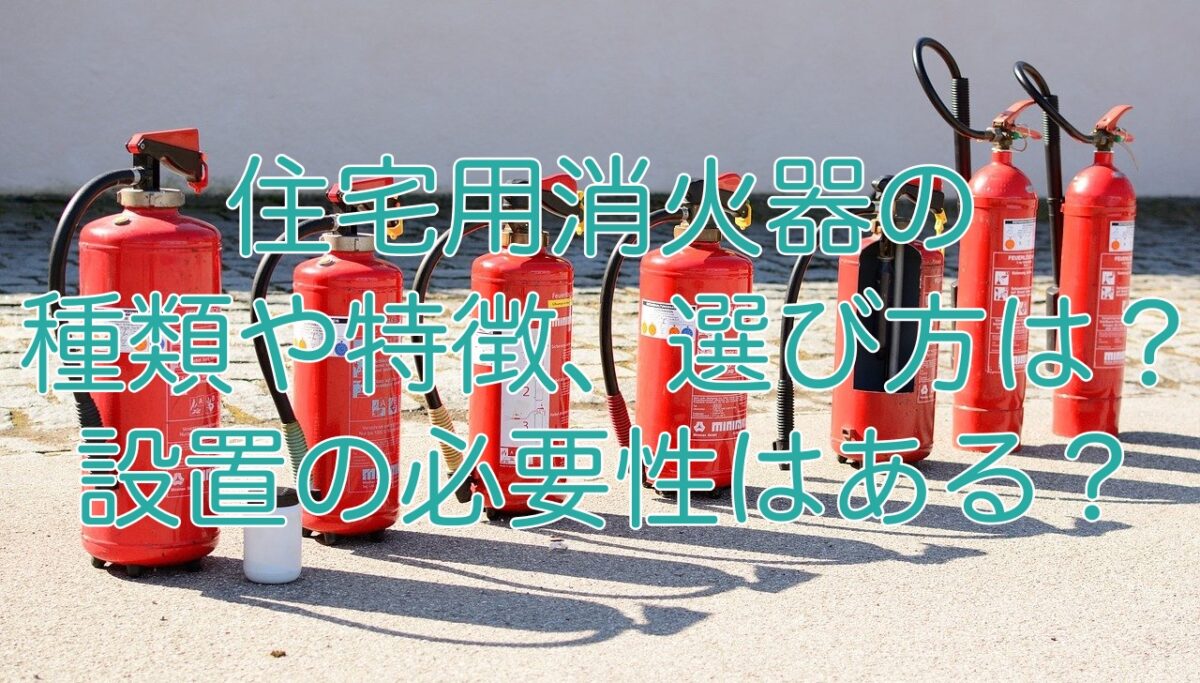火事というものは非常に恐ろしいものです。最愛の人、築いてきた資産、大切な思い出、これから生きていく希望さえも奪うことがあります。
誰一人として燃え盛る炎の中で灼熱の熱さと息の出来ない苦しみを味わいたくありません。不幸中の幸い一命を取り留めたとしても、重度の火傷により思い通りに身体を動かせないもどかしさ、そして引くことのない痛み、それらと今後一生付き合っていくこと余儀なくされるのです。
火事に気付いた時、そしてそれがもう手遅れだと悟った時、為す術もなくただ燃え盛る炎を見続けるしか他なりません。そうならない為にもまずは火事の原因を排除すること、火事に気付いた時すぐに対応できるよう準備しておくことも重要です。
火事の原因
消防庁によると令和3年度における総出火件数は 35,077 件でした。その内建物火災が19,461件ですが、さらにその内訳を見ていくと、
第1位「こんろ」2,603 件(13.4%)
第2位「たばこ」1,703 件(8.8%)
第3位「電気機器」1,398 件(7.2%)
第4位「配線器具」1,181 件(6.1%)
第5位「放火」1,050 件(5.4%)
の順となっています。
毎日の料理や日常にあふれる電化製品、そして一息つくために吸うたばこ。いつもの事でもどこかで慣れと油断が生じます。そしてその瞬間、突然火事は襲いかかってくるのです。
料理中、火のついたコンロから目を離してはいけません。もし目を離す必要があるなら火を止めなければなりません。
電化製品やその配線、日々点検しなければなりません。ほこりが溜まらないよう小まめに掃除を行ってください。故障したまま使うなんて言語道断です。
灰皿に入れたたばこの火が消えるまで見届けることが喫煙者の義務です。寝たばこは絶対にしてはいけません。
初期消火の重要性
もし仮に家が火事になっていると気付いたとして、何をすればいいかわかりますか?まず初めに試みることは初期消火です。それでも消火できないと思えば、そしてすぐに安全な場所へ避難し、すぐに消防署への通報します。
初期消火の三原則
初期消火の三原則というものがあります。
- 初期消火
- 通報
- 避難
- 初期消火
-
火が小さければ、消火活動をすることで火を消し去ることができます。その場合は被害状況を最小に食い止めることができます。
- 通報
-
大きな声で周りの人に火事を知らせることと消防署への通報をいち早く行いましょう。火が小さければ消火活動を手伝ってくれる人もいるでしょう。
- 避難
-
火が大きく、自分ではどうにもできないなら避難するしかありません。被害を最小限にするために、自分や家族の避難と近隣住民の避難を促しましょう。
初期消火の方法
初期消火の方法で、まず最初にすべき行動は燃える原因となるものを絶つことです。
- ガスが原因ならガスの元栓を締める。
- 電気が原因ならブレーカーを切る。
- 燃え移りそうな物があれば、それを退ける。
その後すぐに消火に取り掛かるのですが、自宅ですぐに行える方法は限られています。あえて挙げるとすれば、
- 水を掛ける
- 布団やタオルなどを被せる
- 消火器を使う
が一般的と言えるでしょう。
水を掛ける
初期消火として一番初めに思いつく方法は水をかけて消火することです。しかし「蛇口から水を出し、バケツに汲んで、それを運んで、水を掛ける」という一連の動作が必要になる以上、初期消火を行うまでに時間がかかってしまうことがネックとなります。
まだ火が小さく近くに燃え移る物が無ければ1度水を掛けるだけで消火に至るかもしれませんが、そうでなければ炎がどんどん大きく燃え広がってしまいます。そうなると初期消火どころの騒ぎではありません。もしものために蛇口にホースを繋げ直接水をかけることができるよう準備しておくことが望ましいと言えます。
なお、水を掛けることで逆効果になる場面も存在します。例えば火の付いた油に水を掛けてしますと、油が周囲に飛び散るため炎が一気に燃え上がります。そうなると個人ではどうにも対処しきれないので、逃げる以外の選択肢はありません。
布団やタオルなどを被せる
よくある初期消火の方法として知られている方法は、布団やタオルなどを被せて消火することです。原理は単純で、燃焼物への酸素の供給を遮断することで消火に至るわけです。
しかし、中途半端に酸素を遮断できないと燃料を補給したことに変わりなく、さらに燃え広がるという逆効果になってしまうこともあります。
できれば水で湿らせた布団やタオルを使うことが効果的ではありますが、そこまでの時間を確保できるとは限りませんので、余裕があればという話になります。
消火器を使う
初期消火に最も効果的な方法は消火器を使うことです。火を消すための専用の道具ですから当然と言えます。消火器には「業務用」「住宅用」「自動車用」などの種類がありますが、自宅での使用を考えれば、当然「住宅用」一択でしょう。
粉末タイプの消火器では家の中が汚れるといったデメリットは存在しますが、薬液タイプの消火器であればそのデメリットを解消できます。薬液タイプはタオルで拭き取るなどの後処理で済むので自宅で使用するのに適していると言えるでしょう。
火事が広がる前に食い止めるためにも、自宅へ消火器を常備しておくことが望ましいと言えます。なお、消火器には使用期限がありますので、すでに常備している方は使用期限の確認をしておきましょう。
火災の分類
火災には分類があり、A火災・B火災・C火災と分類されますが、これらの違いは以下の通りです。
- A火災=普通火災
- B火災=油火災=天ぷら油やストーブなど油類が原因によって発生する火災
- C火災=電気火災
住宅用と謳われた消火器であれば自宅での火災を想定されて作られていますので、ABC火災のいずれの火災にも対応した消火器がほとんどです。
住宅用消火器の種類
一言に消火器具と言っても、そこら中で目にすることのある一般的な消火器、それをコンパクトにした住宅用消火器、取り扱いが簡単なスプレー缶のエアゾール式簡易消火具、火の中に投げ入れて使用する投てき用消火用具などが存在します。なお、他にもいくつかのタイプは存在しますが、住宅で使用することを想定された消火器は少ないため、自宅での使用であれば上記の消火器具をオススメします。
ところで、使用される消火剤には強化液タイプ、粉末タイプ、水タイプ、泡タイプ、二酸化炭素タイプなどの種類があります。これらには消火における得手不得手があるため、住宅での使用することを想定するなら強化液タイプもしくは粉末タイプの消火器のどちらかオススメします。
住宅用消火器には色やデザインに凝った消火器が豊富に販売されているため、部屋のインテリアとの調和を乱さず違和感なく常備しておくことができます。
住宅用消火器の特徴と選び方
ここでは「消火器具」「適応火災」「消火能力」「使いやすさ」「放射距離」「使用後の清掃」「使用期限」「点検のしやすさ」「処分のしやすさ」による違いをひとつずつ比較して見ていきます。
消火器具で比較する
どの消火器具を使用するかは、自宅での使用を考えれば以下のの中から選択することが望ましいです。
- 消火器式
- 加圧式消火器
- 蓄圧式消火器
- エアゾール式簡易消火具
- 投てき用消火用具
なお、消火器式は加圧式消火器と蓄圧式消火器に分類されますが、それぞれの違いは以下の通りです。
加圧式消火器
加圧式消火器は特性上、レバーが固いことと放射の瞬間に大きな反動を受けるため扱いにくいという特徴があります。また、容器の劣化や損傷により破裂する恐れがあるため適切な管理が必要になります。倉庫に保管したまま忘れており使用期限を大幅に超えてしまうなどの不適切な管理は絶対にしてはいけません。
蓄圧式消火器
蓄圧式消火器は、加圧式に比べてレバーが固くなく放射の反動が少ないので取り扱いやすく操作性に優れているという特徴があります。加えて、破裂事故のリスクもほとんどないので安全性にも優れていると言えます。さらに指示圧力計が付いていますので点検が容易なことも特徴としてあります。ただしメリットが多い分、加圧式消火器よりも割高となってしまいます。
強化液消火器が特に効果を発揮するのは普通火災と天ぷら油火災ですが、ストーブ火災や電気火災にも対応しています。つまり、住宅での様々な火災の初期消火に対応しているということです。
エアゾール式簡易消火具
エアゾール式簡易消火具は、よくあるスプレー缶タイプの消火器具で、保管場所に困らないことと取り扱いが容易なことが大きなメリットです。天ぷら油による火災の初期消火に特に効果を発揮します。コンパクトなゆえに消火薬剤の量が少なく放射時間が短いことと、消火器に比べて使用期限が短いことがデメリットです。
投てき用消火用具
投てき用消火用具は、火の中に投げ入れるだけなので誰でも容易に取り扱うことができます。消火器やエアゾール式簡易消火具は消火薬剤に残量がある限り広範囲に渡って放射できますが、投てき用消火用具は投げ入れた場所にしか消火の効果がないことは大きなデメリットと言えます。
加圧式消火器よりも蓄圧式消火器のほうが性能面及び安全面で優れているためオススメと言えます。
適応火災で比較する
適応火災とは、どのような火事を想定して作られた消火器かを判断する目安となります。一般的には以下のように分類されています。
- 普通火災:木材・紙・繊維などが燃えるの火災
- 天ぷら油火災:天ぷら油などが燃える火災
- ストーブ火災:ストーブの灯油などによって発生する火災
- 電気火災:電気設備・電気器具のショートなどによって発生する火災
普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災はどれも住宅での火災の主な原因ですが、消火器具によっては消火能力の得手不得手があります。
ですから住宅用消火器の選び方として重要なことは、どういった場所で使用することを想定しているのか、どこに常備しておく予定なのかをあらかじめ想定し、適した消火器具を選択する必要があります。消火器本体のラベルには適応火災が書かれていることもあり判断材料の目安にできるでしょう。
なお、一般的に言えば、消火器具の種類による適応火災は以下の通りとなります。
| 強化液消火器 | 普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 |
| 粉末消火器 | 普通火災・天ぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 |
| エアゾール式簡易消火具 | 小規模な普通火災・天ぷら油火災・電気火災 |
| 投てき用消火用具 | 製品によって異なる |
適応火災で選ぶなら、強化液消火器と粉末消火器は住宅火災における万能な消火器と言えます。
消火能力で比較する
消火器には加圧式消火器と蓄圧式消火器がありますが、これらの消火能力に差はありません。差があるとすれば消火剤の違いによるものとなります。消火剤には強化液タイプと粉末タイプがありますので、それら及びエアゾール式簡易消火具、投てき用消火用具も合わせて比較して見ていきます。
強化液タイプ
粉末タイプ
粉末には、ABC粉末・Na粉末・K粉末がありますが、住宅用としてはABC粉末のものが一般的です。ABC粉末の消火器であれば、A火災・B火災・C火災に対応しているということなので、強化液タイプと同様に住宅での様々な火災の初期消火に対応しているということです。ちなみに、Na粉末とK粉末はB火災・C火災に適応したものになります。
※A火災=普通火災、B火災=油火災、C火災=電気火災
エアゾール式簡易消火具
エアゾール式簡易消火具は、よくあるスプレー缶タイプの消火器具になります。コンパクトで使いやすい特徴がある反面、消火薬剤の量が少ないため大きな火災に向かないというデメリットもあります。
投てき用消火用具
投てき用消火用具もエアゾール式簡易消火具と同様に大きな火災に向かない特徴があります。炎の大きさの目安はおよそ、目線の高さ程度の火までなら消火可能となりますが、投げ入れるだけの消火になるので消火範囲の自由度は少ないと言えるでしょう。
| 強化液消火器 | 住宅での様々な火災の初期消火に対応している |
| 粉末消火器 | 住宅での様々な火災の初期消火に対応している |
| エアゾール式簡易消火具 | コンパクトなゆえ消火薬剤の量が少ないため大きな火災に向かない |
| 投てき用消火用具 | 目線の高さ程度の火までなら消火可能だが、消火範囲の自由度は少ない |
消火能力だけで考えれば、強化液消火器もしくは粉末消火器が適切と言えます。もし消火剤量に不安があるなら住宅用消火器の中には大きめのサイズも販売されていますのでそちらを検討してみてください。
使いやすさで比較する
赤い筒状の消火器を火災訓練などで実際に使ったことある方もいると思いますが、それはおそらく業務用サイズになります。このサイズとなると意外と大きくて置き場に困りますし、持ってみると案外重くて扱いずらいのです。
ですが、住宅用サイズであれば一回り小さく本体重量が2~3kgとコンパクトかつ軽量に作られているため、キッチン周りでも置き場に困ることはありませし、業務用と比べ重量も軽いため扱いやすいという特徴もあります。
エアゾール式簡易消火具であれば住宅用消火器よりもさらにコンパクトかつ軽量な作りになっており、よくあるスプレー缶のようにワンプッシュで使用することができるため、使いやすさとしては抜群と言えます。
投てき用消火用具は、火の中に投げ入れるだけなので誰にでも容易に使用できることから、こちらも使いやすさとしては抜群と言えるでしょう。
| 強化液消火器 | 本体重量が2~3kgのため扱いやすい |
| 粉末消火器 | 本体重量が2~3kgのため扱いやすい |
| エアゾール式簡易消火具 | コンパクトかつ軽量な作りで消火器よりも扱いやすい |
| 投てき用消火用具 | 火の中に投げ入れるだけなので取り扱いが容易 |
使いやすさで選ぶなら、エアゾール式簡易消火具がオススメと言えます。
放射距離で比較する
よくある業務用消火器の噴射距離は、強化液消火器で約3~7m、粉末消火器では約3~8mですが、住宅用消火器では約3~6m程度となります。エアゾール式簡易消火具では約3~5mと少しだけ距離が短くなります。
なお、投てき用消火用具に使用距離はありません。投げることに自信があれば遠くからでも使用することが可能です。これは火に近づかなくても使用可能という意味ではメリットと言えるでしょう。
| 強化液消火器 | 放射距離は約3~6m |
| 粉末消火器 | 放射距離は約3~6m |
| エアゾール式簡易消火具 | 放射距離は約3~5m |
| 投てき用消火用具 | 投げることが得意なら遠くからでも使用可能 |
放射距離で考えると業務用消火器が好ましいですが、実用性を鑑みるに住宅用消火器(強化液消火器もしくは粉末消火器)がオススメです。
使用後の清掃で比較する
使用後の清掃については消火剤の種類によって異なります。粉末タイプの消火器では粉末がそこら中に飛散してしまうので、汚れる範囲が広く後処理に難儀することが想定されます。しかし、薬液タイプの消火器であればそのデメリットを解消できます。薬液タイプはタオルで拭き取るなどの後処理で済むので自宅で使用するのに適していると言えます。
| 強化液消火器 | 薬液をタオルなどで拭き取ることが出来るので掃除が楽 |
| 粉末消火器 | 粉末が飛び散るため掃除が大変 |
| エアゾール式簡易消火具 | 薬液をタオルなどで拭き取ることが出来るので掃除が楽 |
| 投てき用消火用具 | 薬液をタオルなどで拭き取ることが出来るので掃除が楽 |
使用後の清掃だけで考えると、粉末タイプは適していないと言えます。
使用期限で比較する
消火器の使用期限は、住宅用の消火器は製造から5年、エアゾール式は製造から3年のものが一般的です。ちなみに業務用消火器は製造から10年で設計されているものが多いです。使用期限は製造年月日を基に設定されるので、購入の際はできるだけ製造年月日の新しいものを選ぶと少しだけ得をします。
| 強化液消火器 | 製造から5年 |
| 粉末消火器 | 製造から5年 |
| エアゾール式簡易消火具 | 製造から3年 |
| 投てき用消火用具 | 製造から5年 |
使用期限で選ぶなら、住宅用消火器(強化液消火器もしくは粉末消火器)がオススメです。
点検のしやすさで比較する
消火器具を点検をしないこと発生するリスクは、消火できるはずだったのにもかかわらず消火できない事態に陥ることです。と考えると日々の点検というものが大事なのは一目瞭然です。
点検といっても実際に放射するわけにはいきませんので目視での確認になりますが、蓄圧式消火器には指示圧力計がついており、指示圧力計の指針が規定の範囲内に収まっているかどうか判断できるので非常に便利です。一方で加圧式消火器は容器の劣化や損傷により破裂する恐れがあるため適切な管理が必要になります。日々の点検は欠かせません。そういった面では、蓄圧式消火器が優れていると言えるでしょう。
なお、消火器の点検項目については後述していますのでそちらをご覧ください。
点検のしやすさで選ぶなら、蓄圧式消火器がオススメです。
処分のしやすさで比較する
点検で不備があったものや使用期限を過ぎたものは処分する必要がありますが、消火器は通常のゴミとして処分はできないため適切な処分が必要となります。国産の消火器であれば定められたリサイクル方法に従いましょう。
エアゾール式簡易消火具であれば、自治体のルールに則りスプレー缶として処分できるので消火器に比べると簡単に処分することができます。
なお、消火器の処分方法については後述していますのでそちらをご覧ください。
処分のしやすさで選ぶならエアゾール式簡易消火具がオススメです。
消火器の点検と処分

消火器を安全に使用するためには日々の点検が必要となります。また消火器には使用期限が定められていますので、期限を過ぎたものは買い替えもしくは処分する必要があります。
消火器の点検
消火器はいざ使用する際に使えなかったということがないように定期的な点検が必要になります。点検頻度は最低でも半年に一度を目安に点検しましょう。
点検方法については、試しに放射してみるわけにはいきませんので基本的には目視での確認になります。以下の項目を確認しましょう。
- 安全栓が外れてないか。傷や変形がないか
- レバーに傷や変形がないか
- 本体容器の底や側面に傷や変形がないか
- ホースに劣化や損傷、詰まりがないか
- 使用期限が切れていないか
- 指示圧力計の指針は規定のゲージ内に収まっているか(蓄圧式のみ)
異常があれば使用期限内であっても交換しましょう。
不特定多数の人に利用される建造物などは消防法により防火対象物に指定されており、消火器具の設置義務があることや消火器具の点検・報告が義務付けられています。
延床面積が150㎡以上の共同住宅にも消火器具の設置義務と点検・報告の義務があるので、管理会社や大家さんが責任をもって適切な管理をしているはずですが、万が一のときのために消火器具の位置の確認や目視での点検を自分の目で確認しておくと良いでしょう。
戸建住宅は対象外ですが、定期的な点検は必ず行いましょう。
消火器の処分
消火器を買い替える場合
消火器を買い替える場合は、消火器の販売店に引き取ってもらえる場合があります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
消火器を処分する場合
消火器の処分についてですが、ここで記載する処分方法は国産の消火器に限ります。外国製消火器については自治体へお問い合わせください。
消火器の処分には、処分方法や消火器の種類やサイズによって異なりますが、500円から6270円程度の処分費用がかかります。
2009年以前に製造された消火器を処分する際にはリサイクルシールを購入して貼付する必要があります。リサイクルシールの購入できる場所は消火器リサイクル推進センターのホームページから検索できます。料金は500〜600円程度(購入場所によって異なる)で購入できます。
2010年以降に販売されている消火器にはリサイクルシールが貼付されていてるので購入の必要はありません。リサイクルシールは製品の販売時にリサイクル費を徴収するシステムで、不法投棄抑止に役立っています。
なおリサイクルシールには有効期限が記載されており、期限を過ぎたものを処分するには再度購入する必要があります。
消火器の処分方法は主に以下の3つです。
- 特定窓口に引取りを依頼する or 直接持ち込む
-
特定窓口は、主に消火器の販売代理店や防災・防犯事業者が担っており、廃消火器の回収と持ち込みに対応しています。
料金は、引取りなら運搬費と保管費とリサイクル費で2,000円〜3,000円程度になります。持ち込みなら保管費とリサイクル費になり1,000円〜2,000円程度になります。店舗によって異なるのでご確認ください。なお、特定窓口は消火器リサイクル推進センターのホームページから検索することができます。
- 指定引取所に直接持ち込む
-
指定引取場所は、消火器工業会が指定した場所(消火器メーカー営業所や廃棄物処理業者)が担っており、廃消火器の持ち込みに対応しています。料金はリサイクル費のみで処分可能です。なお、指定引取所は消火器リサイクル推進センターのホームページから検索することができます。
- ゆうパックで回収を依頼する
-
ゆうパックでも回収を依頼することができますが以下の注意が必要です。
- 法人での利用はできません。
- 事前の申し込みが必要なので、申し込せずに郵便局へ持ち込んでも対応できません。
- 離島などの一部の地域では対応できません。
- 対応できる消火器は、薬剤量3kg以下または3L以下の消火器です。
- 料金は6,270円(税込)です。(2020年1月6日現在)
なお、ゆうパックで回収する手順は以下の通りです。
- エコサイクルセンターのホームページで申し込みをします。
- ゆうパック伝票や回収箱が自宅に、代金引換で届きます。
- 廃消火器を梱包して、ゆうパックに回収依頼もしくは郵便局に持ち込みします。
エアゾール式簡易消火器具の処分
エアゾール式簡易消火器具は、一般的なスプレー缶と同様の処分方法にて処分できます。各自治体のルールに従い適切に処分してください。
安全データシート
消火器には化学物質が含まれていますので安全データシートが発行されており、各メーカーのホームページなどからダウンロードすることができます。
安全データシート(あんぜんデータシート、英: Safety Data Sheet、略称 SDS)とは、危険性または有害性のおそれがある化学物質を含む製品を他の事業者に譲渡または、提供する際に、対象化学物質等の性状や取り扱いに関する情報を提供するための文書。
wikipediaより引用
事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するためのものなので、自宅で使用する際にはあまり目にするものではありませんが、取り扱いや保管時の注意点、応急処置の方法など知っておいたほうがいい情報もありますので、一度目を通しておくことでより安全に使用することができます。
いち早く火事に気付くために住宅用火災報知器を設置しよう
初期消火の重要性はわかっていただけたと思いますが、火事に気付かなければ意味がありません。そこで必要なのは、火災報知器、ガス漏れ検知器などの設置することです。
あまり知られていないことですが、消防法により全ての住宅に住宅用火災報知器の設置が義務付けられています。
設置場所は寝室と階段で、感知方式は煙式(光電式)の火災報知器を設置することになっています。その他の場所は各自治体の条例によって異なりますが、居間や台所に設置する場合もあります。台所などの煙や湯気が発生する場所では熱式(定温式)の火災報知器の使用が適しています。まだ設置してない人は今すぐ設置しましょう。
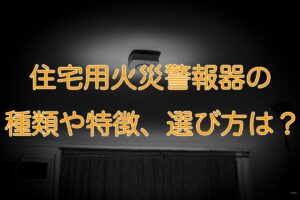
大事な書類を保護するために耐火金庫を使おう
どんなに注意していても100%火事を防ぐことはできません。ですから万が一のためにも耐火金庫で重要な書類や貴重品を火事から守る必要があります。耐火金庫以外には、耐火式・耐熱式のバッグやケース、袋などの商品がありますので、詳しくは以下の記事をご覧ください。

自家用車用の消火器で車内の安全を守ろう
消火器には車載用の消火器もあります。住宅用消火器があるなら車載用消火器もあるのは当然といえば当然と言えます。
住宅用消火器と何が違うのかというと耐振動性と耐熱温度です。振動については「消火器の技術上の規格を定める省令」の振動試験をクリアした消火器が自動車用消火器を名乗ることができると定められています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。